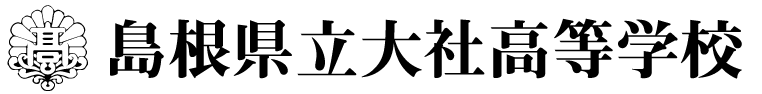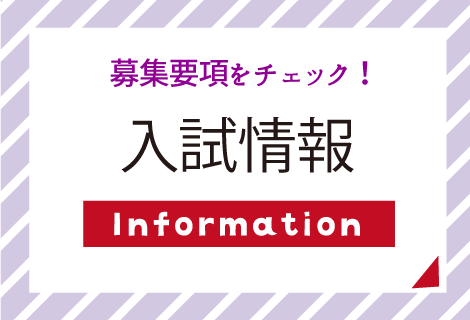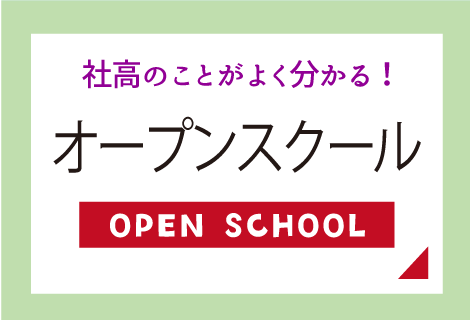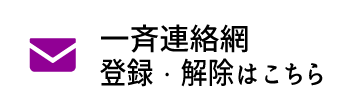令和7年度入学式が行われました
2025年04月09日
春のやわらかな陽射しに包まれた4月9日、本校の体育館にて令和7年度 入学式が行われました。
新たに本校の一員となった新入生たちは、やや緊張した面持ちで式に臨みながらも、真剣な表情で式辞に耳を傾けていました。
以下、式辞の一部抜粋です。
大社高校で過ごす今日からの三年間は、皆さんの今後の人生において、大きな意味をもつ時期となります。そこで、入学にあたり、二つのことをお話ししたいと思います。
昨年度、中学生だった皆さんに向けた学校案内に、「大社高校は○○な学校です」というタイトルの原稿を寄せました。読んでもらえましたか。赴任したばかりの4月、大社高校の特色や魅力って何だろうと考えていたとき、在校生や教職員、そして卒業生や保護者、地域の皆さんは、「ここにどんな言葉を入れるのだろうか」とふと思い、書いた文章です。
学校案内が印刷され手元に届いたときページをめくると、そこには在校生や卒業生からの答えが書いてありました。「チャンスにあふれ、自分の夢に近づける学校」「達成感を感じられる学校」「仲間とともに挑戦できる環境が整った活気のある学校」「熱く夢を追う学校」「やりたいことに本気で取り組める学校」「生徒を本気にさせてくれる学校」など、それぞれ異なった表現で、充実感にあふれた言葉で語られていました。
その後一年間、大社高校で過ごす中で、これらの言葉が偽りのないものであると実感しています。もちろんここに書かれているのはごく一部で、今ここにいる在校生も、これまでの卒業生も、一人ひとりが全く別の言葉を持っているはずですし、たとえ同じ言葉であったとしても、そこに込めた思いは一人ひとり違っていることと思います。
「大社高校は○○な学校です」-新入生のみなさんには、これから勉強や部活動、学校行事などを通じて多くの経験をする中で、ここに入る自分自身のことばを見つけてほしいと思います。前向きで肯定的なことばで語れるような、充実した高校生活を送ることを願っています。
もう一つは、昨年度の入学生にも話しましたが、「だからこそできること」を探してほしいということです。
ずいぶん前のことになりますが、子どもが通っていた中学校で、『五体不満足』の著書で有名な乙武洋匡(ひろただ)さんの講演を聞く機会がありました。乙武さんは、生まれつき両脚と両腕がない「先天性四肢欠損症」という大きな障がいを抱えながら、作家やタレントとして活動され、また小学校教員のご経験もある方です。
その乙武さんが、講演の中で、東日本大震災のときの話をされました。震災後、乙武さんはすぐにでもボランティア活動に参加したいと考えましたが、がれきに覆われた町に車いすの自分が行けば、かえって迷惑をかけてしまうと思い、何もできない、無力な自分にいらだったそうです。しかし、「自分にできないこと」「苦手なこと」で人の役に立とうとしていたことに気づき、障がいがある自分だからこそできることを探し、東北楽天イーグルスの始球式に臨んだそうです。
自分の姿を見て、少しでも東北の人たちに元気になってもらえれば、それが自分にできること。「だからこそできること」がきっとあるはず、と話されました。
学校にはさまざまな個性を持った人がいて、得意なことも苦手なこともそれぞれに違っています。皆さんにはぜひ、「自分だからこそできること」を探し、自分自身のために、周囲の人たちのために使ってほしいと思います。さらに、「この学校だからこそできること」「この地域だからこそできること」「この仲間とだからこそできること」を見つけ、チャレンジしてください。そし、それぞれのチャレンジをお互いに支え、応援し合える、そんな学校を作っていってほしいと願っています。
入学式後の対面式では、まず、生徒会長と新入生代表がそれぞれ挨拶を交わし、お互いに温かい握手を交わしました。続いて、合唱部および吹奏楽部の演奏がありました。
先輩からの歓迎の気持ちと、新入生の決意が伝わる感動的なひとときとなりました。
これから始まる高校生活。出会いと学びに満ちた3年間が、実りあるものになることを願っています。